クラスター株式会社 代表取締役CEO 加藤直人
目標は不老不死? メタバースから見る新たな社会の可能性
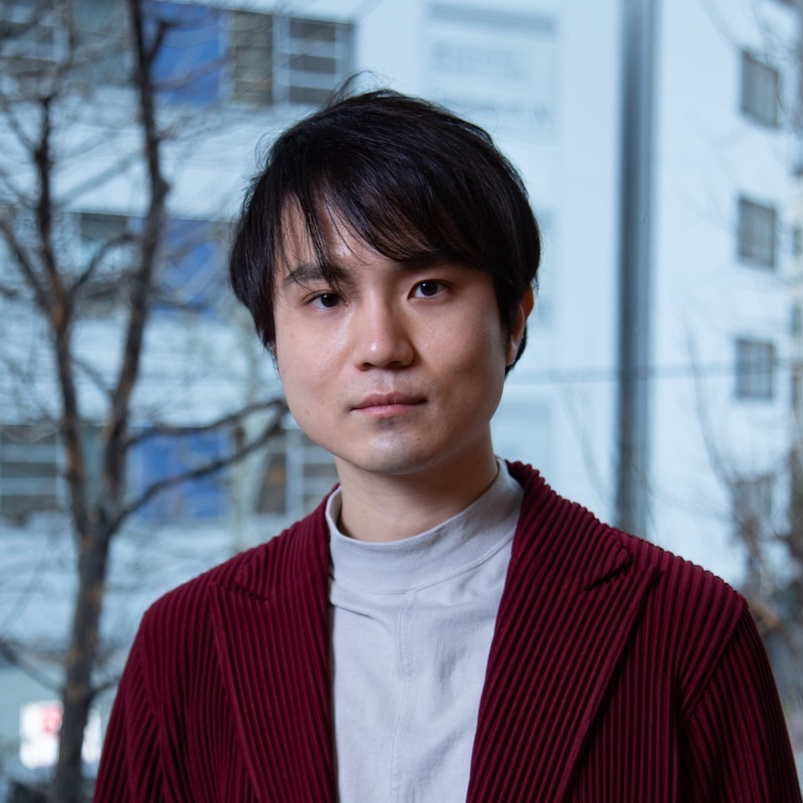
クラスター株式会社 代表取締役CEO 加藤直人 (かとうなおと)
■プロフィール
京都大学理学部で、宇宙論と量子コンピュータを研究。同大学院を中退後、約3年間のひきこもり生活を過ごす。2015年にVR技術を駆使したスタートアップ「クラスター」を起業。2017年、大規模バーチャルイベントを開催することのできるVRプラットフォーム「cluster」を公開。現在はイベントだけでなく、好きなアバターで友達と集まったりオンラインゲームを投稿して遊ぶことのできるメタバースプラットフォームへと進化している。2018年経済誌『ForbesJAPAN』の「世界を変える30歳未満30人の日本人」に選出。同じく2022年、2023年には「日本の起業家ランキング」のTOP20に2年連続で選出。著書に『メタバース さよならアトムの時代』(集英社/2022年)
メタバースの最前線で挑戦を続ける、クラスター株式会社代表取締役CEO 加藤直人さん。子どもの頃から宇宙に憧れを抱き、大学での学びを通して仮想空間技術の世界へ。加藤さんの歩みとビジョンには、テクノロジーが切り拓く新しい社会の姿が見えてきます。
■大学時代に学んだ組織運営の基礎
僕が京都大学に入学したのは2007年。子どもの頃から憧れていた宇宙に対する探求心を胸に、理学部を選びました。学生時代の前半は学生委員会で組織運営を学び、後半は宇宙と量子コンピューター研究に没頭し、今はメタバースの可能性を探る会社を運営しています。
大学生活で最初に力を注いだのは、大学生協の学生委員会での活動です。1年生で入会し、フリーペーパー制作の部署に所属しました。2年生になると、総勢200人規模である学生委員会の代表を任されることになりました。1年次の僕は授業にほとんど出席せず、単位もわずかしか取得していなかったため、代表の誘いを一度は断ったのですが、周囲のメンバーのサポートを受けながら代表としての役割を果たしました。
組織をまとめる中で特に学んだのは、運営の仕組みをしっかり整えることの重要性です。組織が大きくなると情熱や勢いだけでは維持できません。適切な仕組みがあれば、卒業などの理由でメンバーが入れ替わっても、問題なく組織が機能し続けます。この経験は、現在のクラスター株式会社の安定した運営基盤づくりに役立っています。
■研究に没頭し、シミュレーション技術に出会う
学生委員会を引退した後、理学部での研究活動に本格的に力を注ぎました。3年生の頃には宇宙論と量子コンピューターという異なる分野の研究室に所属し、卒業論文を2つ書きました。一見、宇宙論と量子コンピューターは全く別の分野ですが、どちらもコンピューターシミュレーションを活用して現象を再現する点が共通していました。このシミュレーション手法に触れたことが、現在のメタバース事業の土台になっています。
現実の物理現象を仮想空間でシミュレートする技術を通して、人がそこにいるように感じられる体験を作り出すことが今の仕事です。学生時代に学んだシミュレーション技術が、バーチャル空間での現実再現に挑む際の強みとなっています。
■開発への熱意と起業のきっかけ
その後、大学院に進学しましたが、学費や生活費を賄うために始めたアプリ開発への関心が高まり、退学することにしました。2012年から2015年は個人でアプリを開発し、スマートフォン市場の成長期の波に乗ることができました。アプリを開発しながら、ゲームエンジンについてのブログを書いていたところ、ベンチャーキャピタルから出資の提案を受け、2015年にクラスター株式会社を設立しました。
■現在の活動とメタバースで目指す未来
現在、クラスター株式会社は日本発のメタバースプラットフォームとして、多くの企業や自治体に採用され、バーチャル空間でのイベント開催の支援をしています。このように、仮想空間を活用してリアルな体験を提供する中で「仮想空間で現実を生きる」未来を目指しています。僕はこの事業を通じて仮想空間での人々の生活体験を豊かにし、日常に近い形での利用ができる環境を作り出したいと思っています。
更に、最終的に挑戦したい目標は「不老不死」です。僕が想像する不老不死には、2つの方法があります。ひとつは、バイオテクノロジーの力で細胞の老化を防ぐこと。もうひとつは、脳とコンピュータをつなぎ、人の意識をデジタル空間に保存することです。人が現実の体を持たずとも意識を永続させることで、寿命に縛られることなく生き続ける未来が実現するかもしれません。現在、京都大学や東京大学の研究者と共同で、このような夢の技術に向けた研究も行っています。
■大学生へのメッセージ
進路に迷う大学生の皆さんに伝えたいのは「ルールを作る側に立つ面白さ」です。僕は学生時代、数百人規模の組織をまとめたり、新しい技術に挑戦したりしましたが、「ルールを作る」という経験が今も大きな糧となっています。社会に出ると、既存のルールを守るだけでなく、どうすれば新しい価値を生むルールを作り出せるかという視点が求められます。皆さんも自分の手で未来を切り拓き、社会に必要なルールや仕組みを作る力をつけていってください。ルールに従う側から作る側へ、そして社会に影響を与えられる側へ、挑戦を続けてみてください。
学生新聞オンライン2024年11月1日取材 城西国際大学1年 渡部優理絵

東京薬科大学 2年 庄司春菜 / 城西国際大学1年 渡部優理絵 / 東洋大学 2年 越山凛乃



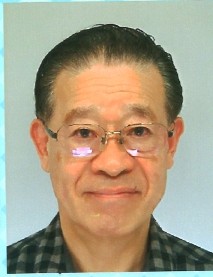






この記事へのコメントはありません。