株式会社Integral Geometry Science 代表取締役 木村建次郎
人類の課題を数学の力で解決し、より良い世界を目指す!

株式会社Integral Geometry Science 代表取締役 木村建次郎(きむら けんじろう)
■プロフィール
10年の歳月をかけて、応用数学史上の未解決問題である「波動散乱の逆問題」を世界で初めて解決することに成功。散らばった波の波紋から物体の立体構造を瞬時に再構成することが可能となり、“人間がものをみること”の根本概念を覆す、数々の観測技術の開発・実現に貢献してきた。散乱場理論をコアテクノロジーとして、医療、エネルギー、インフラ、安全保障等の分野にまで革新をたらすべく、不断の挑戦をし続けている。
数学の力で物体を透視し、数々の社会課題を解決するIGS。代表取締役である木村建次郎さんは、応用数学史上の未解決問題を世界で初めて解決し、革新的な技術を社会に提供しています。そんな木村さんに、起業に至るまでの道のりや研究の魅力、そして未来への壮大な挑戦についてお話を伺いました。
◾️数学との出会い、そして京都大学へ
子どもの頃は、画家に憧れていました。通っていた小学校は、倉敷市の小さな学校でした。近所には風景画を描く先生が住んでいて、いつも大きな犬を連れて旅をしながら絵を描いていました。その自由気ままな生活に憧れ、芸術系の仕事を目指していたのです。しかし、中学生の頃にNHKの宇宙ロケットが発射される番組を観て、「カッコいいな」と感じたことから、宇宙工学を志すようになりました。宇宙工学を学ぶには、日本では東京大学や京都大学が最適らしいと知り、そこから4年間、1日3時間しか眠らず勉強に打ち込みました。その中で数学の面白さに気づき、次第に興味が移っていきました。親から「数学を世の中の役に立つ形で活用しなさい」と助言を受け、最終的に理学部数学科ではなく、工学部を志望することにしました。そして、無事に京都大学工学部への入学を果たしました。
大学在学中は、勉強にも遊びにも全力投球でした(笑)。学者としての基礎を築くために、3,000ページの物理の本を読み、数学の分厚い問題集を次々と解いていました。また、話のネタを増やすために、数えきれないほどのアルバイトを経験しました。アルバイトを通じて、人とのコミュニケーション能力もさらに磨かれたと思います。さらに、自分たちでテニスサークルを立ち上げるなど、積極的に活動していました。こうした忙しい学生生活を送る中で、自然と時間管理が上手になったと思います。また、自分は何かをゼロから始めることが好きなんだと気づくようになりました。
◾️論文との戦い、その悔しさから起業へ
大学のゼミでは、原子やナノスケールで可視化できる顕微鏡を専門に研究している先生の指導を受けるゼミに入りました。研究内容としては、半導体に焦点を当て、その内部構造を透視するための理論や技術の開発に取り組んでいました。当時、半導体の開発において、半導体の「ナノ」の世界で何が起こっているのかがわからないため、どうすればより良いものを作れるのかがわからないという状況でした。そのため、半導体の中で何が起こっているのかを透視する技術が強く求められており、それをテーマに据えて研究を行っていました。
研究の世界では、論文の発表が非常に重要です。同じ研究内容であっても、先に論文を出した方に権威が与えられるからです。過去に一度、論文を提出したものの却下され、その後、海外で同じ内容が発表されたことがありました。その時は、とても悔しい思いをしましたね。
その経験から、「論文が絶対」という現状に疑問を抱くようになりました。そして、特許を取る方が合理的ではないかと考えました。ただし、特許を取得するには資金が必要です。そんな時、教授から「会社を作ってみてはどうか」とアドバイスを受けたのが、起業のきっかけです。私たちの強みは、やはり特許を取得していることです。他社に模倣されない独自の技術を持っている点は、大きな優位性だと感じています。
透視したいと思っていたのは、大学にはいるよりもずっと以前でした。子供の夢のようなものですね。実は、いま私が開発しているあらゆる製品の原理、透視の原理は、理科と数学、特に幾何学が大好きだった子供のころに、想像していた世界のイメージがもとになっています。“世界は虫食いだらけ”、“世界は多角形で埋め尽くされている”という考えです。
いま僕は5人の子供を育てていて、大学でも多くの学生に授業をしていますが、本当に幼い頃の感性というのは後の人生のあらゆるシーンに影響を与えると思います。自分の感性を、本当に大切にしてほしいと思います。
◾️数学の魅力、そして描く未来
数学の魅力は、その厳密さと課題解決力にあります。数学的に証明されているもの以上に確かなものはなく、世の中にある無駄や非合理を最適化・効率化することが数学の役目です。技術が追いつかないジレンマを解決できる点こそ、数学の持つ大きな可能性だと感じます。課題を見つけ、それを解明していく過程は非常に楽しく、まさに「好きだからこそできる仕事」です。もちろん、上手くいかないこともありますが、複数の事業を同時に進めることで成功の確率を高めています。
私たちの会社では、愚直に努力できる人を歓迎します。成果主義を採用しているため、迅速に行動できる人が活躍しています。「理想の組織」とは、効率よく、本能的に動ける状態を指します。また、研究においては時に無給での活動が求められるため、厳しい状況でも前に進める覚悟が必要です。その覚悟がある人こそが成功すると考えています。
将来的には、脳の構造を解明したいという大きな夢を抱えています。やりたいことが尽きることはなく、今の会社(約400億円規模)を5年以内に1兆円規模へ成長させることもその一環です。最終的な目標は、人が自分の死のタイミングを選べる権利を持つ社会を作ること。そのためにも、この世から理不尽な死をなくしたいと強く願っています。
◾️大学生へのメッセージ
「好き」と「得意」は分けて考えるのが良いと思います。得意なことは続けていくうちに、だんだん好きになっていくものです。そして、自分のアイデアを活かせる分野こそ、最終的に楽しめる場になるのではないでしょうか。お金持ちになることがゴールだとは思いません。その人の構想に見合った額のお金を持つべきだと考えています。お金は、世の中のために使える人が持つべきものです。そして、大事なことに取り組んでいれば、後から自然とお金はついてくるものです。やりたいことが見つからない人は、まず指示してくれる人がいる場所に身を置いてみるのが良いでしょう。得意なことや好きなことがまだ見つかっていない人は、とにかく外に出て、自分の知らない世界を減らす努力をしてみてください。
学生新聞オンライン2024年10月28日取材 立教大学4年 緒方成菜

上智大学3年 網江ひなた / 立教大学4年 緒方成菜






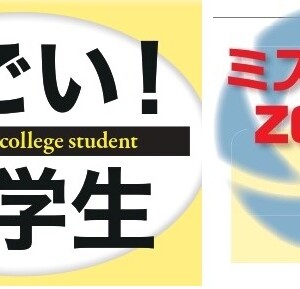



この記事へのコメントはありません。