小説家 朝井リョウ
小説は「雨」のようなもの。気付いたら濡れていて影響を及ぼしている
-scaled.jpg)
小説家 朝井リョウ(あさい りょう)
■プロフィール
小説家。1989年岐阜県生まれ。2009年、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2013年、『何者』で第148回直木賞、2014年、『世界地図の下書き』で第29回坪田譲治文学賞、2021年、『正欲』で第34回柴田錬三郎賞を受賞。最新刊『生殖記』がキノベス!2025の第1位に選出。
小説は「雨」のように心に届くものだ。気付いたら濡れていて自分に影響を及ぼしている。この出どころが分からないからこそ届く距離感が小説にあると語る朝井リョウさん。自身の内面に蓄積されたアイディアを掘り出しながら、新たな物語を生み出し続けている。その執筆のモチベーションなどを語っていただいた。
◾️物語で表現する魅力とは何ですか
物語の魅力の一つに、異なる思想の人々を同じ場に置ける、ということがあります。現実では社会や情報の分断が進んで対話が難しい状況もありますが、小説の中では全く違う価値観を持つ人たちを同じ地平に置けます。また、片方の意見だけでは標語のようになってしまうので、私の作品にはよく対極の者同士の対話が出てきます。それはどちらも自分自身の一部だったりするんですが、異なる思想の人間同士を物語という密室に閉じ込めることで、思いも寄らない言葉が出てきてくれたりするんです。
また、物語にできることとして、「ホースから出る水」ではなくて「雨」として言葉を届けられる、ということもあると思っています。ホースは自分で握っているし、軌道も操りやすいので、狙いを定めて勢いよく水を発射させられます。だけど水の軌道がよく見える分、避けることも可能だし届く範囲が狭かったりもしますよね。それに対して雨は、出どころが分からないまま広い範囲に影響を及ぼせます。これを小説に置き換えると、作者の問題意識やテーマを明かして本を届けるよりも、それらを全部物語で覆い隠して差し出すことによって、そのテーマにもともと何の関心もなかった人たち、むしろ拒否反応を抱いていた人たちにも届けられる可能性があるということです。これは大きな魅力だと感じています。
◾️小説を書くモチベーションは何ですか
このデジタル時代に小説を書くのは、ある種「癖」のようなものだと思います。小説は執筆に時間がかかるし、年に1、2冊しか出版できません。なので、私の場合は、合理的なモチベーションというよりも、「こういうものを書いたらどうなるだろう」という実験的な気持ちが執筆のモチベーションになっています。
また、今は日々新しいニュースが出てきて、時代や状況は絶えず変化しますよね。今日は丸だと思っていたものが明日には四角になり、明後日には三角になるような世の中です。そんな中でも、「この“丸”については考えてしまう」という物事があれば、その執着自体がモチベーションになります。変化だらけの毎日の中でこの“丸”が頭から離れない=書かなきゃいけないってことだ、みたいな感覚です。
◾️アイディアをどのように形にしていますか
普段の生活の中で考えていることが自然と体内に蓄積されていて、それが小説になる感覚があるので、「よし、アイディアを形にするぞ」という瞬間はないんですよね。普段生きている中で、思考のタンクみたいなものが徐々に溜まっていて、それを小説という形式にするためにどうするか、みたいな感覚です。丸太を削って木彫りの熊を作る過程に似ているんじゃないかな。自分の中から作品を掘り出していく、みたいな。
■学生へのメッセージ
最近よく思うのは、学生のときに大切にしていた感覚、たとえば「これくらいの年齢でこういう自分でありたい」とか、「恥ずかしいからこういうことはしないでおこう」みたいな判断基準って、今の自分からは超ズレているんですよね。社会もだけど、自分自身も容赦なく変わっていくんです。価値観も常識も無責任にどんどん変わるので、いい意味で今の自分に固執しすぎず、今“恥”と認識しているものをそう捉えすぎず生きてほしいと思います。
学生新聞2025年4月号 早稲田大学4年 西村夏

東洋大学3年 太田楓華/早稲田大学4年 西村夏/慶應義塾大学3年 松坂侑咲/城西国際大学1年 渡部優理絵/N高等学校2年 服部将昌/東洋大学2年 越山凛乃/上智大学3年 吉川みなみ/立教大学4年 緒方成菜/上智大学1年 張芸那/日本大学4年 鈴木準希





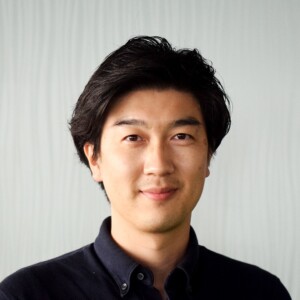




この記事へのコメントはありません。