キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長 皆巳祐一
“人が主役のDX”で、会社を変革

キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部 DX戦略推進室 室長 皆巳 祐一(みなみゆういち)
(※2025年3月取材当時)
■プロフィール
食品メーカーにて営業、マーケティングに従事した後、デジタル化の重要性を感じて2017年キリンホールディングスのデジタルマーケティング部へキャリア入社。
SNS、オウンドメディア運営を担当後、2020年経営企画部DX戦略推進室の立ち上げメンバーとして参画。2023年より現職。
営業やマーケティングの現場を経験し、現在はキリンホールディングス全体のDXを推進する皆巳祐一さん。DXは単なるデジタル技術の導入ではなく、業務や組織の在り方を根本から見直す「変革」であると語る。今回は、自社で進めているDXの取り組みや、大学生へのメッセージを伺った。
私は学生時代、サッカーに熱中しながらアルバイトにも励み、将来は教員を目指して教職課程を履修していました。ただ、就職活動を進める中で「より多くの人・社会と接点を持てる仕事」に魅力を感じ、企業への就職を選択しました。
最初に入社したのは食品メーカーで、営業として約10年間、什器の設置や店舗の支援など、現場業務に従事しました。店舗や施設に足を運び、お客様に喜んでもらうための小さな工夫を丁寧に行っていきました。一つひとつの作業は地味かもしれませんが、「お客様の目に映る場を、自分の手で整えること」に大きな誇りを持って取り組んでいました。
今振り返ると、この経験が「現場を見る」「現場から変えていく」という、現在のDX推進の姿勢につながっていると実感しています。まさか当時、自分が将来グループ全体のDXを担うとは思ってもいませんでしたが、どんな仕事にも意味があり、その積み重ねがキャリアを形作っていくのだと信じています。
その後マーケティング部門に異動し、SNSを活用したデジタル施策を次々と展開し、デジタルの可能性を肌で感じる機会をいただきました。その後、キリンへ転職し、デジタルマーケティング部にキャリア採用で加わりました。戦略的なプロモーションの設計・実行を担いながら、次第に全社的なデジタル戦略にも関わるようになり、社内に新設された「DX戦略推進室」へ。今は「デジタルICT戦略部」へと進化したこの部署で、室長としてグループ全体のDXを統括しています。
キリンで働く中で面白いと感じるのは、「変えたい」「挑戦したい」という想いが歓迎される風土があることです。また、バックグランドの多様なメンバーが組織を超えて連携しあい、価値を生み出そうとする力強さを感じることもキリンならではの雰囲気だと思います。
■キリンが取り組むDX
私たちは、キリンにおける全ての領域を対象としてDXを推進しています。特に、現在話題となっている生成AIに注力しており、2024年11月から、『KIRIN BuddyAI for Marketing』をマーケティング領域で働く従業員に展開しています。キリングループのマーケティング業務に特化した「エグゼキューション開発」「調査・分析」「汎用業務」の3つのカテゴリーに分類された約15種類のプロンプトテンプレートが用意されています。マーケティング業務の担当者は自身の業務に最適なテンプレートを選ぶことで、生成AIを効率的に活用し、迅速かつ質の高いアウトプットを得ることが可能です。また、カテゴライズされたテンプレートを用意することで、生成AIの使用に慣れていない従業員でも、簡単に操作できる点も大きな利点です。今回の『BuddyAI』導入により、国内のキリングループのマーケティング業務に携わる従業員約400名が、業務の効率化とクリエイティブな価値創造に向けた時間の確保を実現できるようになります。生成AIが企業の競争力強化において不可欠な存在になると考えています。
また、全社員のDXリテラシー向上を目指して「DX道場」を開設しています。この取り組みは、単なるeラーニングにとどまらず、白帯から師範までの段位制を取り入れた“学びと対話”の仕組みです。受講者はすでに延べ3500人を超えており、部門長や役員クラスの方々も積極的に参加しています。DXを特別なものとして捉えるのではなく、「日々の業務の中に活かせる身近な力」として浸透させることを目指しています。私たちが大切にしているのは、単にデジタルツールを導入することではありません。社員一人ひとりが、「よりよく働く」ためにDXを活用するという意識と行動の変化こそが、最も重要だと考えています。
■DXが生み出す“働き方の未来”
私が目指すDXの理想は、業務の効率化だけにとどまりません。AIやデジタルの力を借りて、社員が価値を生み出していく業務に集中できる環境をつくることが目標です。
たとえば、議事録の自動作成や資料翻訳といった汎用業務はAIが担い、人は創造性や判断力を発揮できる時間を確保できるようになります。そうした「人とAIの役割最適化」を進めることで、仕事の質とやりがいの両方が高まっていくと考えています。
■大学生へのメッセージ
「やりたいことが分からない」「自信がない」と感じる大学生は多いと思います。私もかつてはそうでした。営業、デジタルマーケティング、DX推進── 今の自分をつくっているのは“やってみた”経験の積み重ねです。
よく「自信がついたら、始めたい」という声を聞きますが、私は「始めたことで、自信がつく」と思っています。小さくてもいい、一歩を踏み出すこと。それが次の道を切り拓き、自分の可能性を広げてくれます。
人生にはリハーサルがありません。すべてが本番です。だからこそ挑戦を恐れず、自分の未来を自分の手で切り拓いていってほしいと願っています。
学生新聞オンライン2025年3月25日取材 津田塾大学2年 石松果林





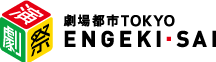





この記事へのコメントはありません。