西日本電信電話株式会社 執行役員 デジタル革新本部長 デジタル革新本部 デジタル改革推進部長(兼務) 小田 孝和
つなぐ力にDXの革新を。NTT西日本が描く未来とは
.jpg)
西日本電信電話株式会社 執行役員 デジタル革新本部長
デジタル革新本部 デジタル改革推進部長(兼務) 小田 孝和(おだ よしかず)
プロフィール
1994年日本電信電話株式会社(NTT)入社。1999年に西日本電信電話株式会社(NTT西日本)勤務となり、西日本エリアのフレッツ網の立ち上げ・NW設備のマイグレーション等に従事。2019年ネットワーク部企画部門長を経て、2022年執行役員デジタル改革推進部長に就任(現職)。2024年より開発・技術系組織を統括するデジタル革新本部長に就任し現在に至る。
DXの力で社会を支える通信インフラの未来とは——。デジタル技術を活用し、地域の課題解決や業務の効率化を進めるNTT西日本。その取り組みや今後の展望について、デジタル改革推進部長の小田孝和氏にお話を伺った。
大学時代は、情報システムやITを専門で学んでいました。研究室のワークステーションで学生がパソコンやサーバーが使えるよう、私はシステム・ネットワークの環境整備や管理を担当させてもらっていました。雑用も多かったのですが、自分が設計構築したネットワークを他の学生が使ってくれて、感謝されたのがとても嬉しかったです。この経験から自分の手で通信の仕組みをつくり、社会を支えるインフラを提供していきたいと考え、当社に入社しました。
入社当時は、ちょうどインターネットが普及し始めた頃で、携帯電話もこれから登場するといった時期でした。インターネットは大学機関などに属する一部の限られた人々が利用するもので、一般家庭にはまだ普及していなかったんです。当時のインターネット環境は通信速度が非常に遅く、ホームページ1ページを開くのに4〜5分かかるような時代でしたね。
私は入社後、主に通信環境・ネットワークをより高速にしていくこと、光ファイバーをインターネットにアクセスする回線に用いること等、インターネットのブロードバンド化に関する開発導入を担当していました。
■多くの人々の頑張りが支えた黎明期のネット環境
今は当たり前のようにインターネットがつながりますが、当時はまだまだ黎明期で、なかなか簡単にネットワーク機器同士が繋がらなかった時代でした。開発しているメーカーのエンジニアに「ここ直してほしい、ここ変えてほしい」などと議論を重ねながら調整し、お客様に使ってもらえるよう実際のフィールドに導入していくことが仕事でした。
導入し多くの皆さんが使ってくれるようになった後も、故障やトラブルなど予想外の問題が起きるものです。その対処にも苦労しましたね。
また、通信設備を苦労しながら構築しても、台風や地震などの災害が起きれば、壊れることもあります。「壊れたら直す」の繰り返しで苦労も多かったです。でも、すべての地域に安定的にインフラを届けることは、私たちの使命でもあるので、大変でも使命感をもってやりとげる仲間たちが一杯います。そんな仲間たちの頑張りがあってこそ、皆さんが当たり前に使える現在のネットワーク環境が実現できていると思っています。
■DXは目的ではなく手段である
現在私が所属するデジタル改革推進部では、DXやAIなどの技術を社内に展開して、業務をサポートする社内システムを開発し、業務を効率化する仕掛け作りを行なっています。
私は、DXとは目的ではなく手段だと思っています。例えば、業務の効率化という目的を果たすためには、組織や人が変っていくことが重要です。そのため、組織や業務の仕組みを変えるための道具としてDXを活用する必要があるのです。
一つの例えになりますが、Aという組織とBという組織があって、その仕組みをDXで変えようとしたとき、両方の組織の役割分担を見直さなければならない場合もあります。その際には各組織の立場を超えて、俯瞰的に第三者の目線としてみる必要もあります。その観点でデジタル改革推進部の果たすべき役割は大きいと思います。
現在、NTT西日本グループでは、通信事業を始めとする業務に約5万人以上の人が携わっています。通信設備を構築する人、故障を直す人、お客様から回線の申し込みを受けたら、その注文を処理する人など、職種はさまざまです。そのような皆さんが効率的に仕事を行えるようにオペレーションシステムを導入し、DXの色々な仕掛けを入れていきます。
DXを進めることで、例えば今まで1000人かかってやっていた業務が100人で出来るようになり、生まれたリソースを活用して「人間にしかできない付加価値のある仕事」をやってもらうことが可能になります。こうした営みを継続することがとても大事です。
■人口減少をはじめ、社会課題をDXの力でどう解決するか
我々、NTT西日本グループは様々な地域に通信環境を提供しています。そして、その各地域には社員・パートナーの皆さんがいて、それらの方々は通信環境を整備・提供するだけでなく、地域のお客様のDXをサポート・手助けすることも行っています。
DXを進めるには通信でつながっている事が大事です。あらゆるものがデジタル化により通信で「つながる」ことが、より大きな価値を生み出します。だからこそ、地域の皆さんのDXを支え、それに寄り添っていくことは私たちの大きな使命だと思います。
その営みが、地域の様々な社会課題を解決することにもつながっていきます。例えば、労働人口の減少をDXやAIによって補うこともできます。インフラの維持が難しくなってきている過疎地域等では、自動運転のバスを導入していくといった仕掛け作りも、各自治体の方と協力して進めています。これに限らず、DXやAIでできることは幅広く、あらゆる場面で社会や人々を支えていくことになります。
また、通信事業は私たちのメインの事業になりますので、そこを強みや接点にしながら、ICT導入のサポートを行ったり、我々のサービスを使ってもらうのはもちろんのこと、お客様のDXを進めるためのコンサルティングを行っています。地域・業種・組織等が異なるさまざまな方々がインターネットを中心とした通信でつながることにより、デジタル化のメリットや影響・効果が更に大きくなります。そのサイクルを回すことがとても重要だと思っています。
今後注目すべき技術は、やはりAIです。現在、AIがものすごいスピードで広がっています。世の中も大きく変わってきています。これまでも、インターネットが登場し、ガラケーがスマホになり、技術の進化で仕事のやり方や世の中の価値観も、ここ10年20年で大きく変わりました。同じく、今後の10年20年も、ものすごいスピードで世の中が変わっていくと思います。なので、やはり新しいものはどんどん取り入れて、自分たちが変化していかないといけないと思います。ダーウィンの進化論のように「強いものよりも変化していけるものが生き残る」と思いますね。
今は変化の時代なので、自分たちも変わっていくし、自分たちが変わることによって進化したノウハウなどを地域や社会に還元することで、一緒になって変わっていきたいですね。
■大学生へのメッセージ
今、生成AIやインターネット検索などを使えば、「調べると簡単に答えがでる時代」です。でも、そこに決して満足せずに、「その答えは本当なのか?」という想いを持ち、その裏側にある本質を是非探求してほしいな、と思いますね。
やはり「苦労した時の経験こそ、現在の自分の成長や力に繋がっている」と経験上思うので、学生の皆さんにもどんどんいろんな苦労を自ら買って出て、さまざまな経験をしてほしいですね。
あとは、好奇心と成長欲求は持ちつづけて、いろんな壁にぶち当たって成長していってほしいです。私がよく言っているのは「いくつになっても日々成長! 年を取っても昨日より今日! 今日より明日!」です。そういう意識で日々私も過ごしています。若い皆さんは成長度合いが大きいと思うので、今を大切にどんどん挑戦してほしいです。
学生新聞オンライン2025年2月21日取材 中央大学3年 向井来幸









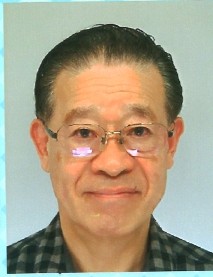

この記事へのコメントはありません。