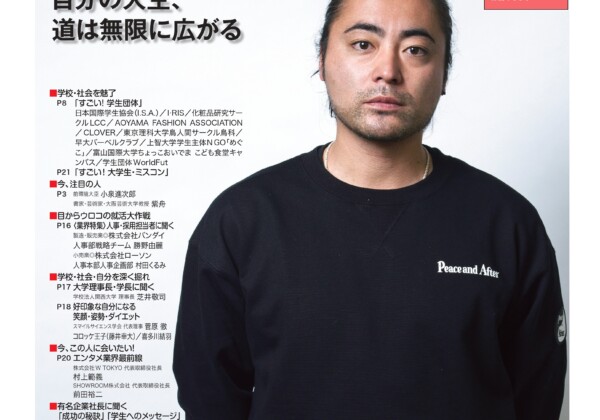SHOWROOM株式会社 代表取締役社長 前田裕二
ライブ配信サービスで世界中の人々に幸せを届けたい SHOWROOM株式会社 代表取締役社長 前田裕二(まえだゆうじ) 東京都出身...

ライブ配信サービスで世界中の人々に幸せを届けたい SHOWROOM株式会社 代表取締役社長 前田裕二(まえだゆうじ) 東京都出身...

株式会社ローソン 人事本部 人事企画部 新卒採用担当 村田くるみ(むらたくるみ) ■プロフィール2014年に株式会社ローソンへ新...

書家は天職。自問自答を繰り返す日々で見つけた道 書家・芸術家・大阪芸術大学教授 紫舟(ししゅう) ■プロフィール日本の伝統文化で...

株式会社バンダイ 人事部戦略チーム チーフ 勝野由麗(かつのゆり) ■プロフィール2014年に株式会社バンダイへ入社。入社後は日...
-600x420.jpg)
自分を小さな枠に収めようとせず、でっかい夢を持とう 学校法人関西大学 理事長 芝井 敬司(しばい けいじ) ■プロフィール198...

「自分の道は自分で決める」決断により責任が生まれ、大きなエネルギーとなる 衆議院議員 前環境大臣 小泉進次郎(こいずみしんじろう...

90年という歴史の積み重ねで日本中を健康にする ■プロフィール 1963年岩手県に生まれ、千葉県で育つ。学生時代に打ち込んだサッ...

コミュニケーションと人間力でコミュニケーションと人間力で プロフィール 1971年兵庫県生まれ。1994年近畿大学商経学部(現・...

ワンチームで世界に通用するブランドを作る! プロフィール 慶應義塾大学院コンピューターサイエンス修了後、博報堂の戦略プランナーを...

人々に楽しんでもらえるサービスを提供する ■プロフィール 大学卒業後、電子写真集などの制作に携わった後、携帯キャリア公式電子漫画...

山田孝之(やまだたかゆき) 1983年生まれ。99年に俳優デビュー。『世界の中心で、愛をさけぶ』『電車男』『闇金ウシジマくん』シ...

冨永愛(とみながあい) 17歳でNYコレクションにてデビューし、一躍話題となる。以後、世界の第一線でトップモデルとして活躍。モデ...