
- 運営スタッフ
- HOME
- 運営スタッフ
運営スタッフの記事一覧


株式会社W TOKYO 代表取締役社長 村上範義
100年を超えて歴史を創る。そのためにNO.1にこだわり続ける 株式会社W TOKYO 代表取締役社長 村上範義(むらかみ のり...

日比美思 「逆境」を「可能性」へ
■プロフィール 1998年9月20日生まれ。神奈川県出身。元Dream5のメンバーとして活躍。グループ活動終了後、女優として活動...

JCOM株式会社 特別顧問 石川雄三
「デジタル×フィジカル=パーフェクト」 ■プロフィール 1985年 第二電電株式会社に入社(現在のKDDI株式会社)。KDDI㈱...

監督 撮影 編集 金子遊・出演 現地コーディネーター 字幕翻訳 伊藤...
映画監督と言語学者という異業種の二人が出会ったことで、実現した映画『森のムラブリ』。本作は、ラオスの密林でノマド生活を送る“ムラ...

衆議院議員 経済財政政策担当大臣 山際大志郎
イノベーションを起こし、生命を大切にできる世の中へ ■プロフィール 山口大学農学部獣医学科卒、東京大学大学院農学生命科学研究科獣...

衆議院議員 復興大臣 西銘恒三郎
復興大臣として福島の今を届け、福島を世界に冠たるものに ■プロフィール 1954年生まれ。上智大学経済学部卒業。沖縄振興開発金融...

映画監督 永井和男 決定権を持つこと。それは、プレッシャーでもあり、...
■プロフィール 1990年9月22日生まれ。大阪府出身。テレビ制作会社を経てフリーに。初監督作『くさいけど「愛してる」』は、国内...

株式会社ドーム タレント&カルチャー部 花田悠太
スポーツを通じて社会を豊かにする ■プロフィール 新卒で川崎汽船株式会社に入社し、株式会社ドームに転職。アメリカンフットボールの...

衆議院議員 法務大臣 古川禎久
夢を追い続けた8年間で心に決めた政治家としてのあり方 ■プロフィール 1965年宮崎県生まれ。東京大学法学部卒業。建設省に入省し...

株式会社インフォマート 代表取締役社長 中島 健
本気になって挑戦すれば、「仕事」は「感動」を生む ■プロフィール 1988年、三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。システム部、海...

監督、脚本、プロデューサー、主演 崔哲浩 作品を通じて、自分にし...
■プロフィール 1979年生。大阪府出身。様々な映画、ドラマ、舞台で幅広く活躍する。2007年に劇団野良犬弾を旗揚げ、主宰を務め...

新潟ベンチャー協会(NVA)ピッチ本選
新潟ベンチャー協会(略称:NVA(Niigata Venture Association))では、起業家や社会人、学生等を対象に...

映画プロデューサー 芥川志帆 「想い」から生まれる映画制作という名の...
■プロフィール 神奈川県横浜市出身。幼少期は劇団ひまわりに所属し、映画などに出演。大学時代はヒラタオフィスへ所属しモデル・女優と...

主演 仲本愛美 ・ 監督 片山拓 基本ふざけているコメディ要素満載の映...
2022年春公開予定の映画『味噌カレー牛乳ラーメンってめぇ~の?』は、10代を中心に人気を集めるモデル・インフルエンサー仲本愛美...

ライバー 勇者べろくん 1日20時間を費やして、ライブに人生を賭ける!
■プロフィール 1994年生まれ。ライバー歴2年、最高ランクのS帯を継続中。3年間社会人を経験し事務所に所属しないフリーライバー...
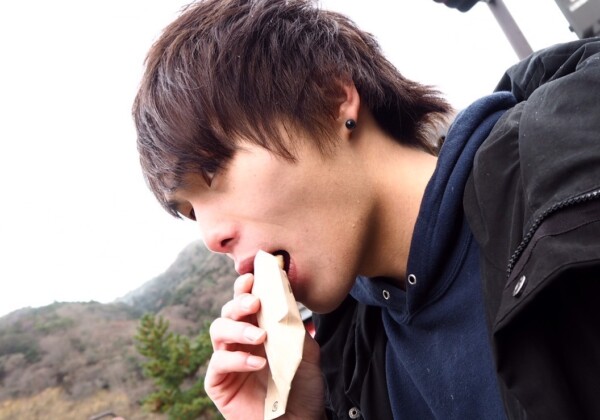
ライバー おしゅん 「話が得意」ではなかった僕が、配信をはじめたワケ
■プロフィール 1999年生まれ。ライバー歴2年。最高ランクS帯。大学を卒業し、就職活動を行わずPocochaライバーとして活躍...

アルフレッサ株式会社 代表取締役社長 福神雄介
「自分で完結的に仕事ができるようになって、初めて魅力がわかる」 ■プロフィール 1999年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業、...

愛知県知事 大村秀章
産業県愛知で、人類社会のための民力をつける ■プロフィール 1960年愛知県碧南市生まれ。東京大学法学部卒業後、農林水産省入省。...

株式会社吉野家ホールディングス 代表取締役社長 河村泰貴
「#外食はチカラになる」プロジェクトの背景と目的 ■プロフィール 1968年大阪出身。1987年広島の高校を卒業後、アルバイトを...

